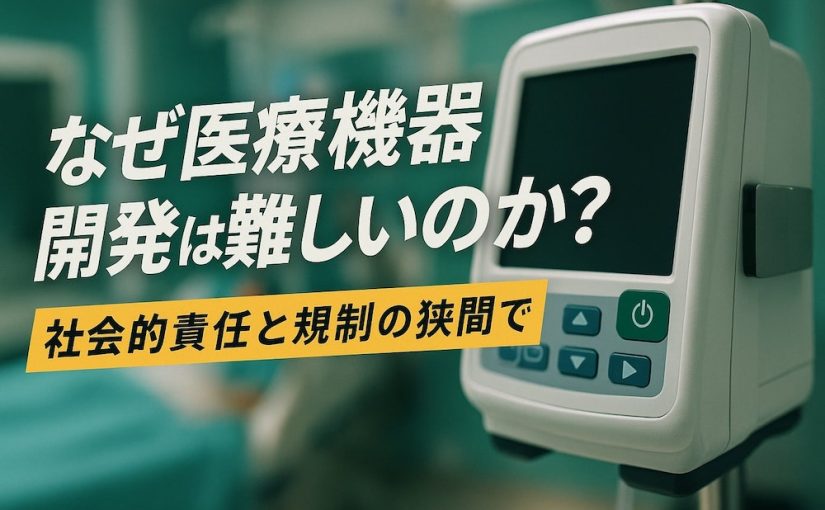最終更新日 2026年1月27日 by ooddee
医療機器開発とは、単なる技術の組み合わせの先にあるものではない。
私が島津製作所で内視鏡開発に携わった30年近くの経験から言えることは、これは「命との対話」なのだ。
「技術者は現場を忘れるな」——この言葉は、私の恩師である故・中村技師長が常々口にしていた言葉であり、この記事の根幹を成すメッセージでもある。
医療機器開発は、社会的責任と厳格な規制、そして現場のニーズという三つの要素が複雑に絡み合う領域である。
一つの医療機器が世に出るまでには、開発者たちの知られざる葛藤と挑戦がある。
そこには、技術の先に人の命があることを痛感する瞬間の連続がある。
本稿では、30年以上にわたり医療機器開発に携わってきた経験から、なぜこの分野の開発が難しいのか、そしてその困難を乗り越えるためには何が必要なのかを考察していきたい。
Contents
医療機器に求められる社会的責任
命を預かる装置としての倫理的重み
医療機器は、人の命を直接左右する存在である。
私が最初に医療機器開発に携わったとき、その責任の重さに息が詰まる思いだった。
一般の家電製品とは異なり、医療機器の不具合は患者の命に直結する。
例えば、内視鏡の光源システムが突然停止すれば、手術中の医師は視界を失い、患者は危険な状態に陥る。
このような状況は絶対に許されない——その緊張感が医療機器開発には常につきまとう。
厚生労働省による医療機器規制の厳格さは、まさにこの命を守るための社会的要請なのだ。
医療機器の開発者は、専門的な技術知識だけでなく、生命倫理についての深い理解も求められる。
ユーザー(医師・看護師・患者)の期待と信頼
医療機器開発の難しさの一つは、多様なユーザーの視点を統合する必要がある点だ。
医師は操作性と診断・治療の確かさを求め、看護師は準備や後処理の簡便さを重視する。
そして最も重要な患者は、安全性と身体的・精神的負担の軽減を期待している。
これらの異なる視点を一つの製品に集約することは非常に難しい。
かつて私が担当した超音波診断装置の開発では、医師からは「より精細な画像を」という要求と、患者からは「検査時間の短縮を」という相反する要望があった。
技術的にはハイエンドな性能を追求できても、実際の臨床現場では使いにくいということもある。
このバランスを取ることが、信頼される医療機器を生み出す鍵となる。
技術者が直面する”見えない責任”
医療機器開発者が背負う責任は、製品の出荷時点で終わるものではない。
1990年代初頭、私が開発に関わった内視鏡システムに予期せぬ不具合が発生したことがある。
幸い患者への影響はなかったが、その夜眠れなかったことを今でも鮮明に覚えている。
開発者は、自分の設計した機器が世界中の患者の体内で使われていることを常に意識している。
この「見えない責任」は数値化できるものではないが、医療機器開発者の精神的負担となる。
同時に、自分の開発した機器が多くの命を救うという喜びも、この仕事ならではのものだ。
技術者としての誇りと、人の命に関わる責任の重さ——この二つの感情が常に共存している。
複雑な規制と認証プロセスの実態
医療機器はなぜこれほど多くの承認を要するのか?
医療機器の開発において、最も時間と労力を要するのが承認プロセスである。
一般的な家電製品と異なり、医療機器は厳格な規制の下で開発・製造・販売される。
なぜそれほど多くの承認が必要なのか——それは医療機器の不具合が直接人命に関わるからだ。
私の経験では、ある内視鏡システムの開発から承認取得までに約3年の歳月を要した。
規制の複雑さは年々増しており、特に2014年の薬事法改正(現在の医薬品医療機器等法)以降、プログラム医療機器などの新たな分野でも規制が整備されている。
この厳格な審査は、時に開発者のフラストレーションとなるが、患者の安全を守るための社会的合意でもある。
医療機器開発者は、この規制の重要性を理解し、早い段階から承認プロセスを見据えた開発計画を立てる必要がある。
PMDAと厚労省の審査フローの構造
日本における医療機器の承認プロセスは、主に独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)と厚生労働省によって管理されている。
承認申請には、品質、有効性、安全性に関する膨大なデータの提出が求められる。
特に新医療機器の場合、臨床試験データも必要となり、その準備だけでも1年以上かかることがある。
PMDAでは「医療機器プログラム総合相談」という窓口が設けられ、開発初期段階からの相談が可能となった。
この制度は、承認までの道筋を明確にするために非常に有用である。
しかし、相談から承認までの標準的なプロセスにおいても、多くの時間と労力が必要となる。
医療機器の分類(クラスⅠ〜Ⅳ)によっても審査の厳格さが異なり、高リスク機器(クラスⅢ、Ⅳ)ほど審査が厳しくなる。
海外との違い:日本独自のハードル
国際的に見ると、日本の医療機器承認プロセスには独自のハードルがある。
欧米では「市場先行・市販後監視」の考え方が主流であるのに対し、日本では「市販前審査重視」の傾向が強い。
例えば、アメリカのFDAは革新的医療機器に対する「Breakthrough Device」制度を設けており、審査の迅速化を図っている。
日本でも2014年に「先駆け審査指定制度」が導入されたが、指定される製品は限られている。
また、海外では認証されている医療機器が日本では追加データを求められることも多い。
これが日本における医療機器の「デバイスラグ」(海外と日本の市場導入時期の差)を生む一因となっている。
グローバル展開を視野に入れた開発では、各国の規制の違いを理解し、戦略的にアプローチすることが重要だ。
現場と制度のギャップ──技術が届かない理由
医療現場のニーズが制度に反映されない実例
医療機器開発における大きな課題の一つは、現場のニーズと規制制度の間にあるギャップだ。
私が経験した例として、ある内視鏡検査用の補助装置がある。
現場の医師たちからは「これがあれば検査効率が上がる」と強い要望があったにもかかわらず、既存の分類に当てはまらないという理由で、承認プロセスに時間がかかった。
結果として、臨床現場で本当に必要とされていた機能が、患者のもとに届くまでに3年以上の遅れが生じた。
また、現場では「この機能とあの機能を組み合わせたい」という要望が多いが、承認された使用方法以外の組み合わせは認められないケースも多い。
このようなギャップは、現場の医療従事者にとっても、開発者にとっても大きなフラストレーションとなる。
医療安全を保ちながらも、より柔軟な制度設計が求められている。
ヒアリングから見える「現場の声」
私が医療機器開発に携わる中で最も重視してきたのは、現場の声を直接聞くことだ。
大学病院や地域中核病院などで定期的に医師や看護師にヒアリングを行うと、カタログスペックとは異なる実用的な要望が多く聞こえてくる。
例えば、「もっと静かな機器にしてほしい」「準備時間を短縮できる設計にしてほしい」などの声は、メーカー側からは気づきにくいポイントだ。
あるベテラン看護師は「患者さんの不安を和らげる工夫がほしい」と話していた。
これは技術仕様書には現れない、しかし患者体験を大きく左右する重要な視点である。
このような現場の声を製品開発に反映させるためには、開発初期段階からの継続的な対話が欠かせない。
しかし、忙しい医療現場と開発チームをつなぐ仕組みは、まだ十分に整備されているとは言えない。
技術的革新が規制に押し戻される瞬間
医療機器開発において、最先端の技術を導入しようとすると、しばしば規制の壁にぶつかる。
AIを活用した画像診断支援システムの開発では、その判断根拠の説明が難しいという理由で、承認が遅れるケースがある。
また、クラウドベースの医療情報システムも、データセキュリティの観点から厳しい審査を受ける。
これらの新技術は潜在的に大きな医療的価値があるにもかかわらず、既存の規制フレームワークになじまないため、実用化が遅れることがある。
技術革新のスピードに規制が追いつかないという現象は、医療機器開発における大きなジレンマだ。
一方で、安全性が十分に検証されていない技術を臨床現場に導入することはできない。
このバランスを取るためには、規制当局と開発者の間の対話と相互理解が不可欠である。
開発の現場から:ものづくりと人づくりの葛藤
チーム内の衝突と合意形成
医療機器開発の現場では、異なるバックグラウンドを持つ専門家たちが一つのチームとして働く。
電気・機械・ソフトウェアエンジニア、医学専門家、薬事担当者、マーケティング担当など、多様な視点が一つの製品に集約される。
私がプロジェクトリーダーを務めた際、最も難しかったのはこれらの異なる視点の間で優先順位をつけることだった。
エンジニアは技術的完成度を追求し、薬事担当者は規制適合性を重視し、マーケティング担当は市場ニーズに焦点を当てる。
こうした価値観の衝突は、時に激しい議論を生むが、それこそが優れた医療機器を生み出すための創造的摩擦でもある。
医療機器開発のリーダーには、これらの異なる視点を尊重しながらも、最終的には「患者にとって何が最善か」という視点で判断を下すことが求められる。
チーム内での合意形成は時間がかかるプロセスだが、この過程を省略すると、後の開発段階で大きな問題が生じる可能性がある。
試作から量産へ:技術者としての苦悩と誇り
医療機器開発においては、研究室レベルでの試作品から実際の量産品へと移行する過程が特に困難だ。
試作段階では完璧に動作していたシステムが、量産環境では予期せぬ問題を引き起こすことがある。
特に医療機器では、信頼性と再現性が極めて重要であり、99.9%の信頼性でさえ十分ではない。
私が経験した超音波診断装置の開発では、試作機で素晴らしい画像が得られていたにもかかわらず、量産段階で画質のばらつきが生じた。
原因は微細な部品の公差だったが、これを解決するために設計を見直し、製造工程を再構築するという大きな決断が必要だった。
このような厳しい状況の中でも、「この機器が多くの患者を救う」という思いが、技術者としての誇りと責任感を支える。
医療機器の試作開発から量産までの複雑なプロセスを乗り切るためには、専門的な知識と経験を持つパートナーとの協業も重要な選択肢となる。
医療機器専門の受託開発・製造メーカーと連携することで、薬事法に準拠した品質管理体制の構築や製造工程の最適化など、多くの課題を効率的に解決できるケースもある。
量産化の成功は単なる技術的達成ではなく、社会への貢献を実現する瞬間でもある。
故・中村技師長に学んだこと
私の医療機器開発者としてのキャリアを大きく形作ったのは、恩師である故・中村技師長の存在だ。
彼は常々「技術者は現場を忘れるな」と言っていた。
この言葉は、単に医療現場を訪問せよというだけでなく、自分たちの開発する機器が最終的にどのように使われ、誰の命に関わるのかを常に意識せよという深い教えだった。
中村技師長は、技術的な問題に直面したとき、「その解決策は患者さんのためになるか?」と必ず問いかけた。
この視点は、時に効率や利益よりも優先されるべき医療機器開発の根本的な価値観だ。
また、彼は若手技術者に「失敗を恐れるな、しかし同じ失敗を繰り返すな」と教えていた。
医療機器開発においては、小さな失敗から学ぶことが、大きな失敗を防ぐ鍵となる。
中村技師長の教えは、技術開発のみならず、チーム運営やリスク管理においても私の指針となっている。
医療機器開発を支える仕組みの可能性
「使える技術」を実現するための官民連携
医療機器開発を加速するためには、官民の連携が不可欠だ。
日本においては、AMEDなどによる医療機器開発支援事業が強化されている。
また、経済産業省による「医工連携事業化推進事業」なども、革新的な医療機器の実用化を後押ししている。
しかし、これらの支援が真に効果を発揮するためには、開発初期段階からの規制当局との対話が重要だ。
PMDAの「医療機器プログラム総合相談」のような取り組みは、開発者が早期から承認プロセスを見据えた開発を行うのに役立つ。
また、大学病院と企業の連携を促進する「医療機器開発支援ネットワーク」も、現場のニーズを開発に反映する重要な仕組みとなっている。
これらの官民連携の枠組みを、より柔軟で効果的なものにしていくことが、日本の医療機器産業の競争力強化につながるだろう。
政策決定者に求められる現場理解
医療機器開発に関する政策決定者には、現場の実態を深く理解することが求められる。
規制の策定や支援制度の設計においては、開発者や医療従事者の声を直接聞くことが重要だ。
また、日本の医療機器業界は輸入超過の状態にあり、特に治療関連機器では海外依存度が高いという課題がある。
この状況を改善するためには、日本が強みを持つ診断関連機器の技術を活かしつつ、治療関連機器の開発も強化する政策が必要だ。
さらに、医療費抑制の圧力が高まる中で、コスト効率の高い医療機器開発を支援する仕組みも求められる。
政策決定者が技術動向と臨床ニーズの両方を理解し、長期的視点で制度設計を行うことが、医療機器開発のエコシステム強化につながる。
次世代に伝えたい「医療機器開発者」の責務
医療機器開発の未来を担う若い技術者たちに、私が伝えたいことがある。
この仕事の最も重要な側面は、技術そのものではなく、その技術が人の命にどう関わるかという視点だ。
「より良い医療」を実現するという社会的使命感が、医療機器開発者の原動力となる。
また、この分野では、多様な専門家との協働が不可欠だ。
エンジニアリングの知識だけでなく、医学や薬事規制の基礎知識、そしてコミュニケーション能力が求められる。
そして何より、患者や医療従事者の声に真摯に耳を傾ける姿勢が重要だ。
次世代の開発者たちには、技術的な挑戦とともに、「誰のための開発か」を常に問い続けることを期待したい。
それこそが、医療機器開発者としての最も大切な責務である。
まとめ
医療機器開発の難しさは、単なる技術的課題にとどまらない。
社会的責任の重さ、複雑な規制との向き合い方、そして現場のニーズと制度のギャップ──これらが複合的に影響し合っている。
私の30年を超える経験から言えることは、これらの困難を乗り越えるための鍵は「対話」にあるということだ。
開発者と医療従事者、規制当局と企業、そして何より患者との対話が、真に価値ある医療機器を生み出す原動力となる。
技術と社会をつなぐ「ことば」の重要性は、ますます高まっている。
最後に、医療機器開発を志す若い技術者たちへ。
この分野は確かに困難の連続だが、その先には「命を救う」という他の仕事では得られない大きな充実感がある。
技術を極めることはもちろん大切だが、その技術が誰のためのものなのか、常に問い続ける姿勢を忘れないでほしい。
故・中村技師長の言葉を借りれば、「技術者は現場を忘れるな」──この原点に立ち返ることで、医療機器開発の真の価値が見えてくるはずだ。